介護福祉士や社会福祉士などの対人援助職ではバーンアウトが多いと聞きます。だからこそ国家試験でもよく出題されているのでしょう。
バーンアウト
バーンアウトは別名「燃え尽き症候群」と呼ばれるように、仕事に対して過度のエネルギーを費やした結果、疲弊的に抑うつ状態に至り、仕事への興味・関心や自信を低下させた状態のことです。
1970年代、アメリカの精神科医ハーバート・フロイデンバーガー(Freudenberger,H.)が論文で「バーンアウト」という造語を発表したのが初でした。
症状
1980年代、アメリカの社会心理学者クリスティーナ・マスラック(Maslach,C.)が、バーンアウトの3尺度から重症度を判定するMBI(Maslach Burnout Inventory)を提唱しています。
・情緒的な消耗感
・個人的達成感の低下
・脱人格化
情緒的な消耗感
バーンアウトすると、消耗感や疲労感が半端ないです。
ものすごい脱力感で仕事を辞めたいと思ったり・・・。
個人的達成感の低下
バーンアウトする人はもともと一生懸命仕事に取り組んできた人が多いです。
なのでバーンアウトすると仕事への達成感が著しく低下してしまいます。
脱人格化
脱人格化というのは他人に対して無情にふるまう非人間的な対応をとることです。
これにより「人を人と思わなくなる気持ち」が生じます。
これは自己防衛反応の一種で、それ以上消耗しないように人に対して思いやりのない対応をしたりするようになるのです。

シニシズム(冷笑主義)ともいうよ。
まとめ
バーンアウトの症状として、「脱人格化」を覚えておいてください。
そして、心理的・精神的な症状はあっても、身体的な症状がないことも併せて覚えておきましょう。
つまり、体の痛みや身体機能の低下、失語症状などは起こりません。
バーンアウトしないために、まずはストレスコーピングです。

問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピングがあったね。
過去問
第36回 問題5
- V介護老人福祉施設では、感染症が流行したために、緊急的な介護体制で事業を継続することになった。さらに労務管理を担当する職員からは、介護福祉職の精神的健康を守ることを目的とした組織的なマネジメントに取り組む必要性について提案があった。
次の記述のうち、このマネジメントに該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 感染防止対策を強化する。
2 多職種チームでの連携を強化する。
3 利用者のストレスをコントロールする。- 4 介護福祉職の燃え尽き症候群(バーンアウト(burnout))を防止する。
5 利用者家族の面会方法を見直す。
選択肢5が正解です。
第31回 問題26
燃え尽き症候群(バーンアウト(burnout))の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 首から肩、腕にかけて凝りや痛みが生じる。
2 人格・行動変化や失語がみられる。
3 無気力感、疲労感や無感動がみられる。
4 身体機能の低下がみられる。
5 日中に耐え難い眠気が生じる。
選択肢3が正解です。バーンアウトの症状として、情緒的な消耗感、個人的達成感の低下、脱人格化の3つがありました。選択肢1のような身体的症状はありません。
次の記事
次は、いよいよ最後の記事。
心肺蘇生法について取り上げます。
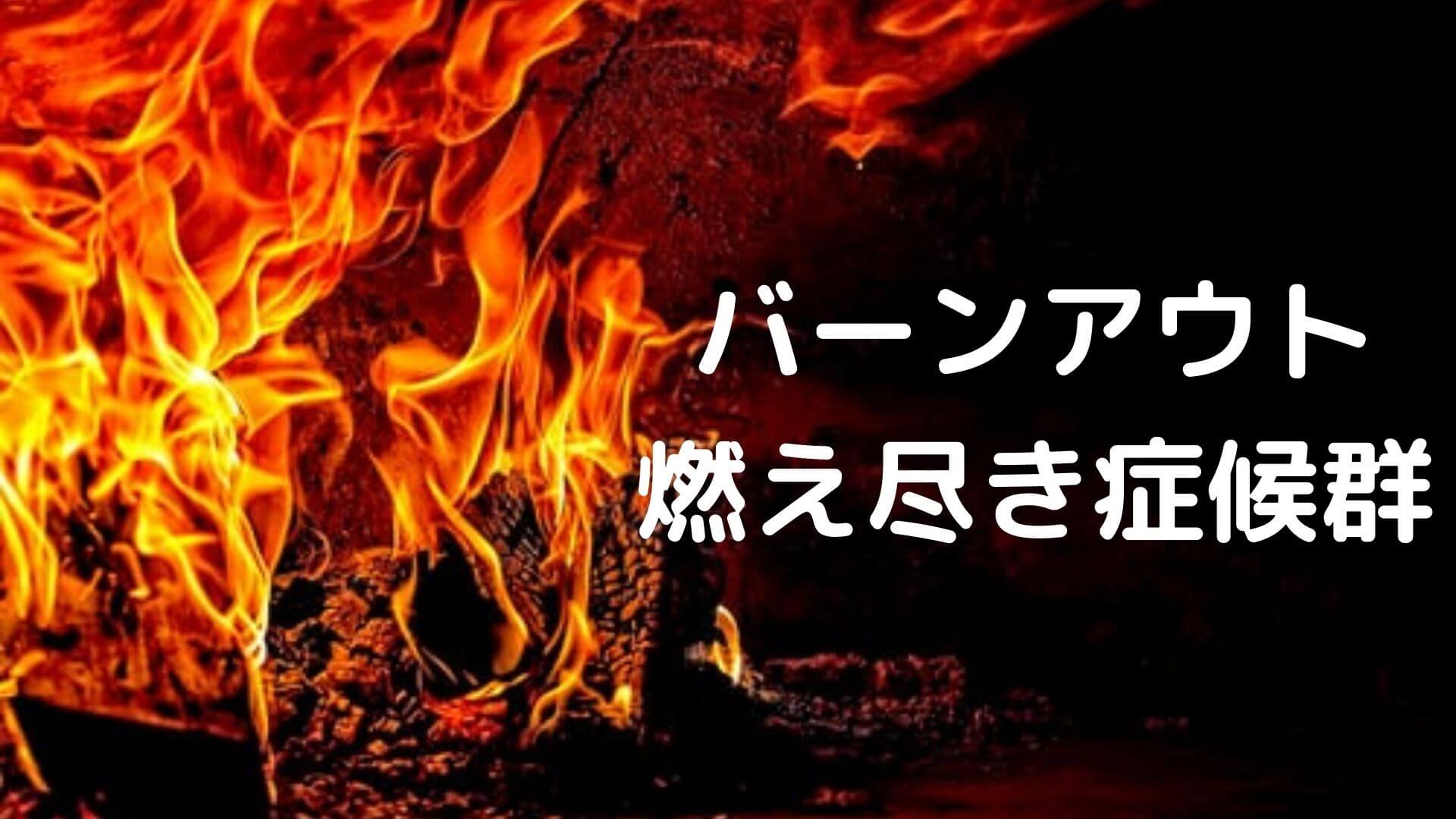



コメント